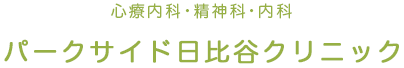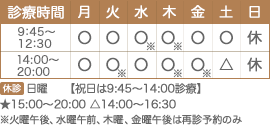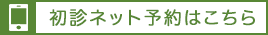叱り方各論(ママ・女性編)
2020/5/8
総論
一般的に以下の傾向があります。
- 感情的
- 主に育児は女の仕事と思っているので、責任を強く感じ、自分が何とかしなくては、と思い、強迫的、ゆとりがなく、いっぱいいっぱいになりやすい。したがって育児のとの適切な距離がとれなくなり、「なぜ、わかってくれないの?」とヒステリックになりやすい。
- 育児の評価が自分の評価と直結して考えやすい。
- 一人っ子が多くなったのも母親が育児に対して、強迫的・依存的になりやすくなった一因。
さらに、もっと詳しく、女性・ママのタイプ別に傾向・対処法を解説します。
各論:母親の叱り方別
① 押し付け・ミラー型
叱り方チェックリスト
- 「お母さんの子供なのになんでそんな事をするの」
- 「あなたがしっかりしないと、お母さんが恥をかくじゃない」
- 「私の子供なんだから、しっかりしなさい」
子どもを自分のコピーと考えてしまう
このタイプは、自分の感情、常識、性格があたかも、自分の子供が全て受け継いでいると勝手に思ってしまうタイプです。
そして、自分の評価を子供の評価と転換してしまいます。
子供の評価が低いと、自分も低い評価を受けていると勘違いして、自分の評価を上げるために、ついつい子供を叱咤激励してしまいます。
また、今現在の自分の感情すら、勝手に自分の子供にもある・理解していると思い込んでしまいます。
よって、「私が今疲れているのを知っているのに、どうしてさらに私を疲れさせることをするの」と怒ってしまう。
子供からすればどうして怒られているのか理解に苦しんじゃいます。
投影同一視
このタイプの母親は、今、自分の感情を子供に鏡のように映す傾向があります。
自分がいらいらしているときに、それを自分の感情と理解せずに、「どうして、うちの子供はいらいらしているんだろう」とあたかも、子供がその感情を持っているよう感じる傾向があります。
自分がイライラしているに、相手がイライラしていてそのせいで、自分がイライラさせられている。
これは投影同一視という心理的動きです。
考え方・叱り方を変えてみましょう
子どもを1個人として、意見を聞いてみましょう
このタイプは、自分が無意識の期待をしていないかを省みる必要があります。
叱ってしまう前に一度立ち止まり、なぜそうしたのかを子供に一度問いただすとよいでしょう。
そうすれば、子供が、自分の予想していたことではないことを考えていてその結果行動したかがわかります。
子供には子供の思考、人格があり、自分のコピーではないと心にとどめておくと良いでしょう。
子供はあなたの子供であって、あなた自身ではないのです。
子どもの考え方がわかり、すべて想定内に
そして普段から、その子の考え、気持ち、感想を聞きだしてあげることも良い事です。
そうすれば、おのずと子供の思考パターンが自分とどう違うかがわかります。
そうなれば、子供がいけないことをしても、「なんで、そんなことすると」と感じず、「この子は、こう考える子供だから、そういう行動をしたのかなぁ」と思えるようになります。
つまり子供の思考パターンがわかっているので、子供の行動を想定内と思える。
想定内と思えるだけで、感情的になることがずっと防げますよ。
②溜め込み爆発方
叱り方チェックリスト
- 「もういい加減にして」
- 「どうしてお母さんの邪魔ばかりするの」
- 「いつも勝手なことばかりしないで」
普段からため込みがち
このタイプは、「いつも」、「ばかり」、「むかしから」等の言葉を使う叱り方をしてしまいます。
自分の感情(怒り等)をぎりぎりまで我慢するタイプです。
子供のストレスをまずは、「あまりくどくど怒ってもなぁ」と感じているストレスを内側に向けて解消しようとする。つまりこらえる。
また、こらえることが美徳と思っていることも傾向です。
しかし、このストレスが重なり、本人は「また、何で何回も怒らせるの」と心の中でつぶやくようになり、最終的に自分では処理できないほどのストレスとなり、ダムの関が決壊するごとくストレスを外側に向けて爆発してしまいます。
急に怒られるので、子どもには理由がわかりません
子供としては、なぜそんなに怒られるのかわからない。
なぜなら、それまで注意されず、勝手に母親が抱え込んでいたからです。
そして、決壊にしたときには、今この時点の子供の悪い点以外に、過去の失敗まで持ち出す傾向があります。
「あの時も、同じ事したでしょ」、「そういえば、一週間前も片付けしなかったでしょ」とか叱ってしまう。
これをしてしまうと、子供は、昔のそんな失敗を今言われてもと困惑してパニックになってしまう。
このようなタイプは、夫との関係が希薄で、ストレスを小出しに出来ないタイプ、カタルシスが苦手なタイプに多い傾向があります。
一人で抱え込むのをやめましょう
解決や意見をもらわず、話すだけで充分です
一人で抱え込まずに、必ず誰かに相談することです。
「夫に相談しても、答えが返ってこないし」、「夫は何もしてくれないし」と考えるのではなく、誰かに助言を受けることを目的ではなく、誰かに話すことを目的として夫に相談すると考えてみましょう。
相談して、相手(夫)に悩みを話すだけでも、大きなカタルシスとなります。
但し、この時大切なのは、相手に「何も言わなくていい(助言しなくていい)から、とりあえず10分だけ、ただただ話を聞いてうなずいて」と事前に伝えておくことです。
そして、聞いてもらう、つまり、状況を共有してもらった上で、何か良き提案を聞く事が大切です。
注意は小出しに
子供に対しては、溜め込まずにこまめに小さく小出しにすることです。
そうすれば、子供も「確かに、いつも言われてるなぁ」と内省しやすいです。
また、子育て以外の日々の自分のストレスも溜め込まずに、出来る限り感情的にならず、なぜいけないのかをはっきりさせて小出しにすることを心がけましょう。
③ 他者評価至上型(マニュアル至上型)
叱り方チェックリスト
- 「みんなが出来るのに何であなたは出来ないの」
- 「周りに怒られるから・迷惑がかかるからきちんとしなさい」
- 「○ちゃんをみならいなさい」
自信のなさから、周囲を気にしすぎる
このようなタイプは、自分に自信がなく、完ぺき主義者に多いです。
自分に自信がなく、また、自分が子供にくだす評価にさえ、自信がないため、他者がくだす自分の子供の評価に異常に過敏になってしまいます。
また、平均を、周りの平均に合わせすぎて、常に自分の子供を叱る判断基準を周りの平均基準に合わせすぎる傾向があります。
そして、このようなタイプは完ぺき主義者にも多く。
より完璧を求めるため、他者の評価で自己の完璧さを補う傾向があります。
あなたの子がナンバー1
まずは、自分の子供が一番と信じること。そして、さらによくなるために、周りの意見、雑誌のマニュアルなどを参考にすると思いましょう。
つまり、依存から、利用に変えることです。
何ができなかったではなく、何ができたかを見てあげましょう
完ぺき主義者だと、常に失敗体験を感じてしまいます。子供もそうです。だって、完璧なことなんてありえないわけですから。
「100点(完璧)から、何点マイナスか」と考えるのではなく、「±0から何点プラスか」と考えるようにしましょう。
減点主義から加点主義へ。
たとえ、比較する場合でも、悪い部分・出来ていない部分だけを比較するのではなく、良い部分・出来ている部分も同時に比較することが大切です。
その場合でも、あくまでも加点方式で。
「あなたは、ここは飛びぬけて優れているけど、ここはみんなとおんなじくらい出来て素晴らしいね。そしたら、あそことあそこもみんなと同じように出来ればもっと素晴らしいね。」
大人も同じように、自信は何よりも勇気になり、何事にも乗り越えようとする力になります。
子供ならば親に言われればなおさらであり、親が想像できないほどの才能を開花させるかもしれませんよ。
④ 直感(視覚)ホルモン支配型
叱り方チェックリスト
- 「うるさい」
- 「全然だめ」
- 「なにやってるの」
感情が先走ってしまう
このタイプは、感情を表す言葉から子供にぶつける叱り方をしてしまいます。
しかも、子供が片付けをしなかったり、失敗を視覚で確認した瞬間、その現場がなぜそうなったのかを理解する前に感情が先回りしてしまいます。
叱り方も、感情・ダメ出しの言葉から入ってしまう。
しかも、子供が口答えしたものなら全てを全否定する。
つまり、子供が悪いことしたことは当然あるが、それ以上に自分がいらいらしているはけ口として子供を叱っていることが多いかもしれません。月経前などが典型例ですね。
今の自分がどんな状態か理解する
まずは、叱る前に、今の自分の精神状態を正しく把握することです。
「己を知れば百戦危うからず」とうい言葉があるように、例えば、月経前だからいらいらしてしまっていると理解するだけで子供を叱ってしまうことからだいぶ距離が開けられます。
「あ~、生理前だしなぁ。子供が悪いんじゃなくて私がいらいらしているのかもねぇ」と流すことも大切です。
流すときも、実際その場で流そうとせずに、ちょっと物理的距離も離すことも大切です。
いらいらしているときに、その場で流そうとしても見えてしまっているので、直感的に怒ってしまいます。
だったら、その部屋を出てみるとか、家の周りをぐるっと一周してみることもお勧めです。
裏わざとして、歯磨きすることもお勧め。
たとえ叱らなくてはならない時も、最初に感情を表す言葉をもってこないことです。
このコロナ自粛の中、家族の為に頑張っているママ・女性のご参考・一助になれば幸いです。
文責:パークサイド日比谷クリニック院長 立川 秀樹
プロフィールはこちら
※本掲載内容を許可なく転載することを禁じます
- 最新情報
- コラム「~2026年元旦~多忙でも、ストレスを和らげる方法」を掲載いたしました
- コラム「『うつ』で医療機関を受診する目安」を掲載いたしました
- コラム「新しい、不眠症の治療薬(ボルズィ)が登場~2025年11月版~」を掲載いたしました
- 院長コラム
- 桜と心の不調
- 産後うつ病
- ストレスに強くなる、意外!?な方法(前編)
- ストレスに強くなる、意外!?な方法(後編)
- 新型コロナ第2波に対しての心構え~SOCで乗り切ろう~
- 新型コロナ第2波に対しての心構え~SOCアプローチ実践~
- 新しい双極性障害の治療薬が登場しました
- テレワーク後「会社に行くのが億劫な人たち」
- 感謝
- テレワーク不安・不眠GW前後で、ストレスがどのように変化したか~葛藤対象の変化~
- GW前後での変化~マズローの欲求5段階とは~
- テレワーク不眠・不安と、マズローとの関係
- テレワーク不眠・不安がテレワークうつへ移行
- テレワークうつにならないためには
- 休校や自粛でストレスを抱える子どもたちのために
- ADHD:薬物療法の意義
- ADHD:薬物療法の種類
- 叱り方総論(パパ・ママ編)
- 叱り方別(ママ、女性編)
- 叱り方別(パパ、男性編)
- 自粛による昼夜逆転生活の防止
- うつ状態と怠けの違い
- 健康な食事しか食べられない人たち~オルトレキシア
- テレワークうつ
- 「テレワークうつ」にならない為には
- テレワークうつ 医療機関受診の目安
- 新型コロナ関連ストレスが、心に及ぼす影響
- 新型コロナストレスと不眠
- 新型コロナストレスと抑うつ
- 新型コロナストレスと過食
- コロナ過食を防ぐための8か条
- 新型コロナに感染しない為には(精神医学的アプローチ)
- 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、どのくらいの期間生存するのか?
- 新型コロナ関連ストレス長期化することによって生じる問題
- 他の敏感な人たち~シゾイドパーソナリティ、発達障害~
- 新しいうつ病の治療薬が
登場しました! - HSPと過覚醒
- HSPと適応障害・うつ病
- 敏感すぎて疲れてしまう人~HSP~
- 高照度光療法
- ストレス対処方法概論
- ストレス対処方法各論
- ストレス対処方法各論
~問題対処外向型~ - ストレス対処方法各論
~問題対処内向型~ - 熱中症と漢方
- 不眠にだるさ、食欲低下…
夏バテと“夏うつ”の違いとは? - 年代別でみる心の病
- パニック障害とパニック発作
- ストレス性で心を病むとは?
- ストレスに強くなるには
- こころの病気の診断方法
- こころの病気の治療
- 朝起きと健康の関係
- 朝起きられないが、夜元気な人たち~夜型人間~
- 早寝ノススメ
- ストレスと過覚醒
- 五月病と過剰反応
- うつ病と食事
- 気象病と寒暖差
- 抜毛症でお悩みの方へ、切なるお願い
- 適応障害とうつ病の違い(一般論)
- 適応障害とうつ病の違い(当方解釈)
- 適応障害とうつ病の違い(治療編)
- 抗うつ薬のやめ時
- 気象病(R4年春の傾向)
- 抜毛症になりやすい人
- メニエール病と過覚醒
- コロナ禍での五月病対策
- 運動でうつ病予防
- 睡眠と運動
- SNS断ちでうつや不安が改善
- コロナ後遺症と過覚醒
- コロナ後遺症とブレインフォグ
- ブレインフォグの原因
- 「ヘアロス」とは
- 敏感すぎて疲れる人へ~気疲れを和らげるコツ~
- 抜毛症と現在バイアス(Present bias)
- コロナ後遺症なぜ長引く?~その①~
- コロナ後遺症なぜ長引く?~その②~
- 抜毛症~髪は、なが~い、友達です~
- 気象病と眠気~2023年梅雨の傾向~
- 毛髪疾患サポートハンドブック
- 夏バテと漢方
- 不安(パニック)でMRIが受けられない
- 夏バテと睡眠負債
- 午前中眠くて仕方ない人へ有効な治療薬!?
- ブレインフォグとセロトニン(新型コロナウィルス感染後遺症)
- 年末年始
- 抜毛症治療Q&A(2024年新春版)
- 悪夢に感謝?!
- コロナ禍、心の健康を保つ秘訣~会話時間の大切さ~
- 睡眠の質と夢の関係
- コンサルタントが病まない為には
- 冬季うつ病とは
- うつ病と漢方
- 気象病2024年速報
- パニック障害と漢方
- 不眠症と漢方
- 気象痛と漢方
- 夏バテと漢方
- 特殊な抜毛~眠っている時に間に髪を抜いてしまう~
- うつ病と高照度光療法~日光浴のすすめ~
- 12月30日~プレ大晦日~
- 新年
- クービビック(2024年12月発売の不眠症治療薬)
- 月経前増悪(PME)
- 脱毛症(円形脱毛症など)とストレス
- 脱毛症と漢方
- 吐き気・不眠・涙が出る症状の原因とは
- 抜毛抑制ウィッグ!!
- 電車や会議室で吐き気、息が苦しくなる~テレワーク終了による弊害~
- 過食症におすすめな食事~前編~
- 過食症におすすめな食事~後編~
- 抜毛症外来の現状
- 気象病~今年の特徴(R7年)~
- 睡眠と筋肉~筋肉時計~
- 過食症の傾向(18年間の動向)その1~過食の成り立ち~
- 新しい、不眠症の治療薬(ボルズィ)が登場~2025年11月版~
- コラム「『うつ』で医療機関を受診する目安」を掲載いたしました
- コラム「~2026年元旦~多忙でも、ストレスを和らげる方法」を掲載いたしました
- 病気のコラム
- 摂食障害
- 不眠症
- 食べないと眠れない症候群
夜間摂食症候群(NES) - 寝ている間に食べてしまう
症候群 - 社交不安障害(SAD)
- 統合失調症
- 適応障害
- 抜毛症
- 依存症
- ADHD(注意欠陥・多動症)
- 仮性認知症
- 更年期障害
- 更年期障害に伴ううつ状態
- 非定型うつ病
- 気象病
- 舌痛症
- 心身症
- 月経前症候群
- 慢性疲労症候群
- うつ病
- ディスチミア型うつ病
- 新型うつ病
- 仮面うつ病
- 冬季うつ病
- 強迫性障害